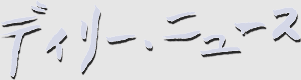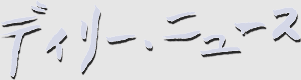|
Q: “フィリピンの花嫁”という社会的なテーマを取り上げていますが、むしろそのテーマに関心を持っている自分自身を描いている事に驚きました。なぜこういった作りにしたのですか?
AI: 私はどちらかというと、今回のように実験的な作品を作る事を心掛けています。私はもともとシアターグループに属していて、ナレーションの入った一般的なドキュメンタリー映画の制作を習っていました。しかし、私が作る映画に関してはそれらを全部断ち切って、新しい、創造性のある、もっと個人的な感情を表現する手法を試みたいと考えており、なるべく今までの伝統的な手法に捕われないよう注意しています。前・中・後といったまっすぐな構成の作品ではなくて、どこから始まって、どこで終わりなのかが見当もつかない、ミックスされた作品にしたいと思っています。
Q: 彼女たちを撮っている、イラガン監督自身の悩みや苦しみを映画の中からは感じましたが。
AI: 私は政治的に主張するという事を進歩的な大学で教わりました。だから私は今まで“アジアの花嫁”と呼ばれる人に対して、批判的な立場をとってきました。彼女達は被害者なのだという見方、貧しい出の彼女達がお嫁さんとして山形に来ることが、自分の生活を良くする方法だと信じて彼女達は来たのだという見方、人身売買だという見方をするなど、ネガティヴなものとしてずっと考えていました。そして彼女達は何も知らされないまま、山形に連れて来られたのだと思っていました。しかし、彼女達の事を知るにしたがって、彼女達自身が事情をよく理解した上で、自ら決断したのだという事が分かってきたのです。私達は彼女達を一方的に被害者だと決めつける事もできなければ、彼女たちを山形に連れてきた(嫁として迎える)男達を非難する事もできないのです。
Q: 異国の知らない男の元へと嫁がされるという状況の中で、なぜ花嫁達はあのように明るく幸せなのだと思いますか?
AI: 国外に出る事は国内での生活が良くないからであって、彼女達は自分が日本に来て幸せなんだよ、と見せたい気持ちがあるのではないかと思います。本当はちょっとだけ、幸せなのかも知れません。彼女達が日本に来るのは大きな犠牲を払っているはずなんです。文化的に全然違うところに連れて来られた事自体、犠牲なわけです。そういった事を思い出させないで彼女達にインタビューすると、「ここに来て幸せだ。お金もあるし、家もあるし、子供もいるし、そのお金もフィリピンにいる家族に送金できる程幸せです。」と、みんな口々に言ってくれます。でも「あなた本当に幸せなの?」と聞いた時に、“リアルハッピー”という答えが返ってくるとは思いません。
次の作品は本作でも登場するマチルデさんを撮った作品になるという。また山形で監督と新作に会えることが楽しみだ。
|